まなびの目標🎯 : 「情報モラル」「ネットコミュニケーション」「インターネットでの被害と加害」「サイバー犯罪」「不正アクセス禁止法」を理解して使えるようにしよう!
1. 情報モラル
2. コミュニケーション
3. ネットコミュニケーションの特徴
4. 情報社会における、個人への影響や被害、加害のリスク
5. サイバー犯罪
6. 不正アクセス禁止法
7. 確認クイズ
1. 情報モラル
情報モラルとは、情報社会で、安全かつ適正に利用するための考え方と態度のことを指します。
💡情報モラルの基本的なこころがけ
・人に迷惑をかけない
・人を不愉快にさせない
・安全に気を付ける
匿名でも無責任な発言や誹謗中傷は避けるべきで、悪質な場合は犯罪となることもあります。
また、犯罪に関わる、あるいは年齢制限があるなどの危険なサイトへのアクセスを制限するフィルタリングも重要なルールです。
2. コミュニケーション
情報技術が発展し、様々なコミュニケーションを行うことが可能になっています。
例えば、会話、電話、Web会議、手紙、電子メール、SNSなどがあります。
 📢やり取りの時間に焦点を当てると
📢やり取りの時間に焦点を当てると
・会話、電話、Web会議は、リアルタイムで行う「同期型」
・手紙、電子メール、SNSは、基本的に「非同期型」
📢場所に焦点を置いてみると
 ・直接会話は「直接コミュニケーション」
・直接会話は「直接コミュニケーション」
・電話やWeb会議は「間接コミュニケーション」
📢人数に焦点を当てると
発信者対受信者 1対1の個別型、1対多のマスコミ型、多対1の逆マスコミ型、多対多の会議型
このように、コミュニケーションは方法や状況によって異なる特性を持ちます。
3. ネットコミュニケーションの特徴
インターネット上では、誰でも簡単に情報発信できるため、誤情報やフェイクニュース(虚偽情報)が拡散することがあります。発信内容や発信源を確認し、信憑性(しんぴょうせい)を見極めることが重要です。
インターネットへの投稿は記録性が高く、削除しても完全には消えません。また、匿名性が高いため、発信者の特定が難しい一方で、無責任な言動がトラブルを招くこともあります。これらの特性を理解し、情報を正しく読み解き発信するメディアリテラシーを身につけることが重要です。
4. 情報社会における、個人への影響や被害、加害のリスク
💡情報社会での被害
フィッシング詐欺は、偽のメールやWebサイトを使って、銀行口座やパスワードなどの個人情報を盗み取る手口です。近年、被害が急増していますので、個人情報の入力には十分注意してください。
人の心理や行動の隙をついて、不正に情報を入手する手口であるソーシャルエンジニアリングがあります。
また、ATMやパソコン画面を肩ごしにのぞき見てパスワードなどの個人情報を盗む行為(ショルダーハッキング)、警察や上司などになりすます、あるいはゴミ箱をあさって情報を盗む行為など、これらの手口は、身近に起こる可能性があり、注意が必要です。

💡情報社会が個人に与える影響
インターネットや情報技術の発展は便利な一方で、次のような心理的・社会的・身体的な影響を与えることがあります。
・テクノストレス:パソコンやスマホ、インターネットの利用の普及による人が感じる心理的・身体的なストレス全般のこと
・テクノ不安症:新しい技術に対応できないことへの不安
・テクノ依存:情報機器に過度に依存し、日常生活に支障をきたす
・インターネット依存(ネット依存)::長時間のインターネット利用がやめられず、生活に影響を及ぼす
・VDT障害:パソコンやスマホなどの長時間作業によって起こる肩こりや視力低下など
💡インターネット利用に関する加害
インターネット上でのやり取りも、対面と同じかそれ以上に正確さと思いやりを意識することが重要です。投稿前に内容をよく考えましょう。
Web上の特定の対象に多くの人が批判し、その状態がおさまらなくなることを炎上といいます。ネット上の情報は簡単に消えないため、投稿前に慎重に確認し、不適切な表現がないか精査することが重要です。
5. サイバー犯罪
インターネットやコンピュータを悪用した、サイバー犯罪も増えています。
📢サイバー犯罪の例
・不正アクセス・なりすまし(他人のIDやパスワードを盗み、システムに侵入する)
・コンピュータ・電磁気的記録犯罪(マルウェア(コンピュータウイルスなどの悪意あるソフトウェア)を利用し、端末を不正操作してデータを破壊・改ざんする)
・ネットワーク利用犯罪(フィッシング詐欺、架空請求・ワンクリック詐欺などインターネットを悪用した詐欺)
6. 不正アクセス禁止法
サイバー犯罪の不正アクセスに関する法律があります。
不正アクセス禁止法(不正アクセス行為の禁止等に関する法律)とは、他人のIDやパスワードを不正に利用してシステムへ侵入する行為を禁止する法律です。
 💡不正アクセス禁止法の5つの禁止行為
💡不正アクセス禁止法の5つの禁止行為
・不正にアクセスする行為(第三条)
・他人のIDやパスワードを不正に取得する行為(第四条) ※取得するだけも禁止です!
・不正に入手したIDやパスワードを第三者に渡す行為(第五条)
・不正に入手したIDやパスワードを保管する行為(第六条)
・IDやパスワードの入力を不正に要求する行為(第七条) ※フィッシング詐欺はここに該当!
7. 確認クイズ
Q1. 情報モラルの基本的な考え方として、適切でないものは?
- インターネット上では何を書いても自由

- 人を不愉快にさせない

- 人に迷惑をかけない

![]() 正解!
正解!
![]() 不正解!
不正解!
インターネット上では何を書いても自由
Q2. 不正アクセス禁止法で禁止されている行為として適切でないものは?
- 不正に取得したIDやパスワードを第三者に渡す行為

- 友人の許可を得てパスワードを共有する行為

- 他人のIDやパスワードを不正に入手する行為

![]() 正解!
正解!
![]() 不正解!
不正解!
友人の許可を得てパスワードを共有する行為
Q3. フィッシング詐欺の手口として最も正しいものは?
- コンピュータウイルスを使ってデータを破壊する

- ネット上で高額な商品を売る詐欺行為

- 偽のメールやWebサイトを使い、個人情報を盗み取る

![]() 正解!
正解!
![]() 不正解!
不正解!
偽のメールやWebサイトを使い、個人情報を盗み取る
Q4. ソーシャルエンジニアリングの具体例として適切でないものは?
- セキュリティソフトを使ってパスワードを守る

- なりすまして電話でパスワードを聞き出す

- ATMの画面を肩越しにのぞき見してパスワードを盗む

![]() 正解!
正解!
![]() 不正解!
不正解!
セキュリティソフトを使ってパスワードを守る
Q5. ネット上で、発信者の身元がわかりにくいことを何と言いますか?
- 匿名性

- 非同期性

- 即時性

![]() 正解!
正解!
![]() 不正解!
不正解!
匿名性
確認クイズは、いかがでしたでしょうか?閲覧いただき、ありがとうございました!
1か月目の2週目、お疲れさまでした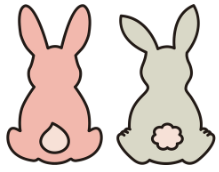
※本記事 教科書該当範囲
| 教科書名 | 該当章 |
| 新編情報Ⅰ(東京書籍) | 1章 4. 情報モラル, 6. 傷つかない傷つけないために, 9.情報化と私たちの生活の変化, 10. よりよい情報社会へ |
| 最新情報I(実教出版) | 第1章 1節 情報社会, 第2章 1節 メディアとコミュニケーション, 第4章 2節 情報セキュリティ |
| 高校情報ⅠJavaScript(東京書籍) | 第1章 3. 法規による安全対策, 第2章 7.コミュニケーションとメディア |
| 高校情報ⅠPython(東京書籍) | 第1章 3. 法規による安全対策, 第2章 7.コミュニケーションとメディア |
本サイトは、教科書をベースに構成しています。使える「情報Ⅰ」を目指し、毎週月曜日に新しい記事を発信予定です。
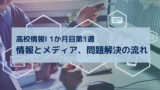
Instagramフォローをお願いします!
Instagram: https://www.instagram.com/hira_labo/
本記事に対し、お気づきの点ございましたらお問い合わせよりご連絡頂けますと幸いです。

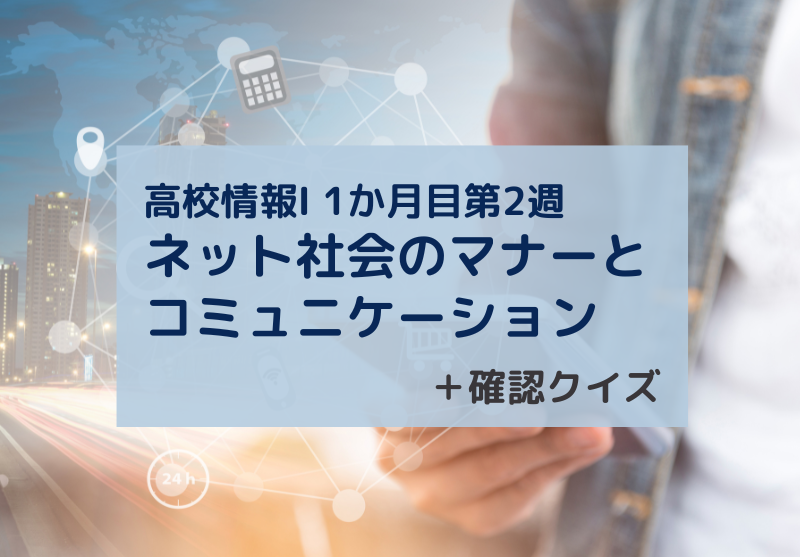
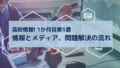
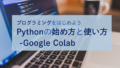
コメント